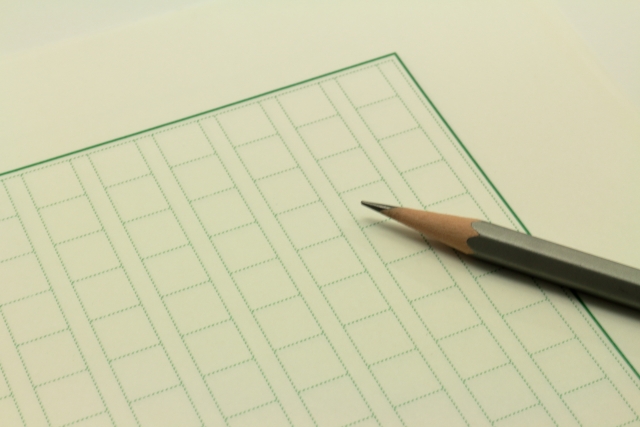ひたちなか市の学習塾・個別指導塾・進学塾 受験予備校常勝の塾長の吉村です。
高校受験って大変ですよね。
小学校でやっていた勉強というのはものすごく簡単な内容で、しかも学校でやっているテストも冗談みたいな誰でも90点以上が取れるようなテストだったわけです。
それが急に校内順位を出したりとか、塾テストと言えば偏差値がどうのとか、そういう世界に放り込まれるわけですから、それまで経験がない子供にとっては、高校受験の勉強というのは相当大変に感じるはずです。
大人でもそうですけれども、初めてやることというのは大変ですよね。
幼いうちは、去年できなかったことが今年はできるようになったとか、個人的な成長の喜びで話は済むわけですね。
ところが中学校になるとどうなるかと言うと、どこかの誰かが勝手に決めたルールや内容を覚えなければならなくて、しかもそれが出来なければ基準に届かないということで、まるで不良品みたいな評価を受けてしまうわけです。
要するに尺度が変わってしまったわけです。
幼児とか小学生ぐらいまでは、できたとかできなかったとかいう尺度が、本人の成長そのものにあったわけですね。
だから去年は書けなかった漢字が今年は書けるようになったとか、割り算ができるようになったとか、特に絶対評価になった現在では、他人との比較ではなくて自分ができるようになったかどうか、ということが小学生ぐらいまでの価値観だったわけです。
ところが、中学校に入って何が起こったのかと言うと、建前は絶対評価だと言いながら実態の部分では順位を出したりとか、要するに相対評価的な価値観なわけですね。
なぜそういう変化をしなければならないのかと言うと、中学校っていうのは義務教育の最終段階ですから、要するに世の中に出るための準備をしなければならないわけですね。
そうすると親子の間で「よくできるようになったね」とかそういう問題ではなくて、
世の中が要求するレベルに届いたか届かなかったかということが問題になってくる。
つまり、基準が自分ではなくて、世の中の方になってしまった。それが中学校の段階なのですね。
だから、高校受験の勉強の大変さというのは、それまでは親子の間だけで通用していた価値観を変えて、世の中が要求するレベルに合わせなければならないと言う、価値観の変化、尺度の変化、パラダイムシフトなわけですね。
このことは世の中全体の競争が激しかった保護者の時代にはあまり考えなくても良かったことかもしれませんが、ゆとり教育以降、特に考えなければならないことだと思います。
「世界にひとつだけの花」という歌が学校で合唱されていた、あの辺から急激に変化してきたのだと思います。
個性があるなどということは当たり前の話で、その上で世の中には競争があって、常に他人と比較されている現実を否定できないわけですね。
例えば花王の洗剤よりもライオンの洗剤の方がいいとか、このリンゴよりもこっちのりんごの方が美味しいとか、そういうことと同じように、 a さんの方が b さんよりも数学ができるとか、言ってみれば商品価値が違うわけですから、他人から見れば常に比較されてしまうわけです。
高校受験の基準というのはそういうことに基づいていて、 Aの大学の方が B の大学よりも優秀な人が集まるとか、C の会社の方がDの会社よりも売り上げも多くて待遇もいいとか、世の中のあらゆることが常に比較されているわけですね。
山の中にこもって誰とも接しないで悟りを開くんだと言ったように、世の中の基準から離れてしまうのであれば、こういうことは考えなくていいんでしょうけれども、
そうではなくて普通の文化生活を行うとか、そういうことであれば、要するに普通の人であろうとするならば、
基準というのは常に自分以外のところにあって、 常に自分は誰かと比較されるんだ
ということを、受け入れざるを得ない。
誰かと比較され続ける世間・世の中にデビューするための準備をすること。それが中学校の段階なんだと思います。
だから小学生が中学校に上がると、とても大変なように感じるんですね。
部活などでむやみやたらに中学校が忙しいのも、世の中にデビューするための準備として必要なのだともいえますね。
幼児から小学生段階と言うと、ペットみたいに可愛い可愛いと周囲の大人たちが可愛がる、そういうことで済みましたけれども、世の中にデビューする日が近づいてくるとなれば、そんなことでは済まなくなる。
戦前であれば丁稚奉公などということもありましたけれども、戦後の日本国憲法と教育基本法の下で義務教育のシステムになってからは、世の中にデビューするのは中学校卒業の時だとなりました。
それでも、そんなのは最低レベル。社会から見れば、使い物にならないわけです。
だから中学校卒業と言うと、社会的に見ればほとんどゼロで、中学校しか出ていなくて社会にデビューするとなれば、小学校しか卒業していないのと大して変わらない。
ほとんどゼロから叩き上げるしかないということになりますね。
一方、高校というのは義務教育ではないので、世の中のレベルに近づけるしかないわけですね。
それでも世の中の最も低いレベルぐらいな感じで、本当に世の中が知的な分野での即戦力として要求しているレベルと言うと、 大学のレベルぐらいな感じで、それでも世の中全体から見れば初歩の段階なわけです。
そうすると大学ということになると、頭を使ってやっていく仕事の最低レベル、高校ということになれば頭をあまり使わなくてできる仕事の最低レベル、そのように個人の発達段階には関係なく、世の中が要求してくるレベルというのが決まってくるわけですね。
だからそれに適合できる人は合格ということになって、適合できない人は不合格ということになる。
言ってみれば、元々みかんの等級が決まっていて、その等級に適合したものは高い値段で売れて、適合できなかったものは安い値段でしか売れない、最低レベルにも満たなかったものは廃棄処分になる、そういうことにとても似ているわけです。
なぜそういうことになるかというと、人間は誰でも何かと何かを比較してしまう。どっちの方がいいとか悪いとか、それがなくならない限りは常に誰かと誰かが比較されるわけで、そうである限り、そんなの嫌だと泣きわめこうが、 受験みたいなものはなくならないわけですね。
幸いにして人間はみかんではありませんから、合格できなかったとしても廃棄処分にはなりませんが、あなたの意思とは関係なしに、大学には大学の基準があって高校には高校の基準があって、それに「あなたが」合わせられるか合わせられないか、というのが試験制度になっているわけですね。
そこで現実的には、社会が即戦力として求めるレベルと中学校卒業のレベルというのは、あまりにもかけ離れているわけですね。
専門的な知識と能力を持って、社会が求める最低レベルの状態になっているためには、頭を使って生きていくのであれば大学レベルと決まっている。
そのまた最低レベルに届いていると言えるレベルもあって、それが大学の合格レベルなわけですね。
その本質は選別なわけです。
そのレベルと中学校のレベルとはかけ離れているので、そのギャップを埋めようとなると、
中学校3年間で勉強した内容の3倍以上の内容を頭に詰め込まなければならない
ということになる。
量的に3倍以上だというだけではなくて、内容的にも難しくなっていくわけですね。
高校受験は大変だとか言いますけれども、大学受験はその3倍ぐらい大変なわけですね。
高校受験が大変だと感じるのは初めての経験だから大変だと感じるというだけのことで、
大学受験の場合には内容的量的に、本当に大変になるわけですね。
そこで普通に考えれば、高校に合格したらおめでとうというのは合格発表から入学までの短い期間だけで、一度合格してしまうと、そこからは高校受験の3倍以上の大変さが待ち構えているわけです。
高校受験で終了だという風に考える人がいますけれども、それは高校卒業でもいいんじゃないかというような考え方によるもので、大学受験の大変さを本当の意味で分かっていないから なんですね。
大学と言っても、定員割れしているような大学もたくさんありますけれども、そういうのは名前も聞いたことがないような私立大学の話で、
誰もが名前を知っているような有名私立大学であれば、日本中から受験者が殺到するわけですね。そうするとかなりの競争倍率ということになる。
しかも、そういう有名私立大学というのは大都市に集中していて、東京のような大都市には所得が高い人がたくさんいますよね。 すると、お金がありますから、わざわざ国公立大学に行こうとは考えずに、できるだけ少ない試験科目でできるだけ少ない労力でできるだけブランド力がある私立に行こうと考える人がたくさんいるということになります。
お金の力によって、できるだけ少ない試験科目でできるだけ少ない労力でできるだけブランド力がある私立に行こうと考えるというのは、所得が高い都会型の方針だと思います。
人は易きに流れるというのは田舎でも同じことですから、できるだけ少ない試験科目でできるだけ少ない労力でできるだけブランド力がある私立に行こうと考えるのは田舎の人も同じなわけですけれども、 残念ながらそういう人は日本中に大量にいるので、大変な競争にさらされることになります。
大学受験のレベル自体が高いがためにハードルが目いっぱい上がっているところで、さらに競争原理が働くわけですね。
一般に田舎の方が所得が低いですから、どうしても国公立大学を第一志望にする傾向が強いと思いますが、国公立大学を第一志望とするとなれば、できるだけ少ない試験科目と言ってもセンター試験というのがありますので、5教科の勉強をせざるを得ないわけですね。
2020年から大学入試の試験が新しい制度に切り替わり、どの教科も問題文がやたらに長くなって、今までよりもますます長文読解の能力が問われるようになりますけれども、
文系の大学を志望する人であっても数学から逃げられず、理科や社会の勉強からも逃げられないわけですから、共通一次の時代から一貫して、国公立大学というのは5教科全体のオールマイティな力が問われているわけですね。
国公立大学には5教科総合で偏差値50以上の得点力が必要になりますけれども、例えば東京大学や京都大学といったようなトップの大学になると、文系の人であっても数学の力が相当なレベルになっていないと、そもそも合格ができないわけですね。
そういうわけですから、効率的な勉強というのはもちろん必要ですけれども、高校生の80%以上が挫折する・捨ててしまうと言われている高校の数学を、国公立大学の受験生は捨てることができないわけです。
理系志望の高校生でも、国語力とか英語力も問われてくる。
何と言うか、逃げようがないわけですね。
その逃げようがない5教科すべてが、片っ端から長文読解の世界になっていく。
2020年からの新しい国公立大学の大学入試の制度は、数学と理科から逃げられないのは元々ですけれども、さらに、 日本語や英語で書かれた長文を読解していくという能力が、さらに問われていくことになるのですね。
そのような流れは、実は私立大学についても言えて、新テストに参加する私立大学はもちろんのこと、文部科学省はそのような方向性を取っているので、学校独自のテストを展開している早稲田大学などが、はっきりとそれに追随しようとしているんですね。
読解力というのは文章を斜め読みすることではなくて、一文字一文字のレベルまで正確に読んでいくということですね。
ということは、数学だろうが理科だろうが、5教科全てにおいて国語の読解力のような能力が問われているということで、パターン暗記のような能力は、あまり問われなくなる、ということになるわけですね。
国公立大学でも私立大学でも、要するに大学入試全体がそういう方向性にありますので、間違いなく高校入試もその流れになってくるはずです。
私立中学の中学入試もますますそういう傾向になっていくでしょうね。
そこで考えて欲しいのですが、これから年々、パターン的な勉強ばかりをしていて文章をまともに読んでこなかった人は、受験のための勉強になった時に、ものすごく苦労することになるということです。
読解力というのは突き詰めていえば思考力そのものということで、ここで言う思考力というのは結局のところ文字情報の情報処理力、ということになるのだと思います。
文字情報の情報処理力というのは、教え込まれたことを再現するということではなくて、文字で書かれた情報を自分の頭で処理して、文字でアウトプットするということですね。
ということは、読解力を鍛えるというのはどういうことかと言うと、文字情報をインプットしてそれをアウトプットする能力を高めるということなのですね。
大学入試はまもなく、高校入試もまたそれに追随して、数学だろうが理科だろうが読解力が問われてくる時代がやってきた、という時代の変化
に対応するためには、
文章を目で追いかけるだけではなくて、自分が考えていることを文章で表現するという訓練が大切になってくると思います。
ということは、読解力を鍛えるということと文章力を鍛えるということはほとんど同じことで、読解だらけの問題に対応していくためには、要するに自分の手で自分で考えた文章を書かなければならない。そういうことになると思います。
誰かから詰め込まれたことを暗記するだけの勉強をしてきた人は、これからますます対応できない状況になっていく。
大学受験でも高校受験でも、文章を読むことと文章を書くことの訓練が、ますます大事になると思います。
そういうことは一朝一夕にできることではありませんので、できるだけ早く遅くとも中学生のできるだけ早い段階で、そういう訓練をしていかなければならないでしょうね。
文章を読むことと文章を書くことは、実は小学生のうちにその基礎が作られますから、中学生になってからでは遅すぎるとも言えます。
高校に入ってから大量の内容と難しい内容と、中学校の3倍以上の膨大な勉強していかなければならないわけですから、
さらにその勉強の内容が暗記というよりも「文章を読んで書かせる」という方向にどんどん進んでいくわけですから、
その勉強のやり方自体を、長文読解に対応していくような勉強のやり方に変えなければならない。
受験予備校常勝は、従来から長文読解に対応していくような勉強のやり方を続けてきましたけれども、
高校生・中学生・小学生・全てにおいて、読むことと書くことを訓練する指導方針を、今まで以上に、ますます徹底していきたいと思っています。
でもできることならば、近い将来、国公立大学や有名私立大学に子供を進学させることを考えるのであれば、
小学校低学年の段階から、読むことと書くことを、訓練していく必要があると思います。
そういう指導が遅れて、一度駄目な状況になってしまったものを立て直すのは、本人も指導する側も相当な痛みを伴うことになりますので、
読めない書けないという状況になってしまう前に、読むことと書くことが苦にならない・得意な状況にしてしまうのが一番です。
私は中学高校大学と、とにかく本の精読とか文章を書きまくることを長年やっていて、その結果として日本三大新聞社を就職先として絞り込みましたけれども、 残念ながら新聞記者として採用されるためにはあと一歩及ばず、毎日新聞社の販売局つまり日本全国規模のマスコミの営業部門に採用と言う結果になりましたが、若い頃の読みまくって書きまくったという経験が、塾長の指導としてこれからますます重要になっていくということに、使命のようなものを感じています。